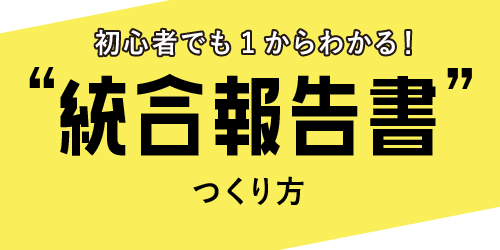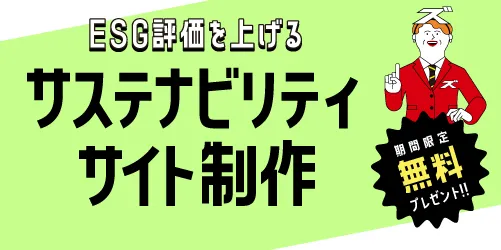「ガイドライン準拠」から脱却し、
真の「価値創造」を。企業価値を最大化する、
戦略的統合報告書へ
複雑化する国際基準(ISSB/SSBJ)、高まる投資家の要求、限られたリソース。
その高度な課題に、アサヒコミュニケーションズの専門チームが伴走します。
- ISSB/SSBJ
基準対応 - TCFD/TNFD
開示支援 - 人的資本
開示支援
なぜ、毎年多大な労力をかけても、
統合報告書の評価が上がらないのか?
プライム上場企業の情報開示担当は、統合報告書発行の最前線でさまざまな課題に直面しています。
もし一つでも当てはまるなら、それは貴社だけの課題ではありません。
体制・リソースの“壁”
-
「人員不足が深刻だ」
統合報告書を発行している企業の46.4%が「発行にあたる人員の不足」を課題としています。専門知識を持つ人材が限られ、多くの担当者が他の業務と兼務しているのが実情です。その結果、日々の情報収集や調整に追われ、統合報告書の根幹である戦略的な内容の検討や価値創造ストーリーの深化まで手が回らない状況に陥っています。
-
「部門間の調整が限界だ」
統合報告書の発行は、財務、経営企画、サステナビリティ、人事、各事業部など、社内の各部門を横断するプロジェクトです。しかし、それが故に「社内の合意や調整が困難である」という課題が常に付きまといます。各部門から集まった情報をただ並べるだけでは、一貫したメッセージは生まれず、単なる情報の「羅列」に終わってしまいます。これでは、その企業が本来もつ統合された価値創造の姿を伝えることはできません。
-
「PDCAが機能していない」
多くの企業で、統合報告書が完成した直後は疲労感から「燃え尽き症候群」に陥り、客観的な振り返りがなされないまま時間が過ぎてしまいます。そして、次年度の制作が始まる直前に慌てて社内での振り返りを行うため、本質的な課題を特定できず、毎年同じような構成や表現が繰り返される「企画のマンネリ化」を招いています。これでは、投資家からのフィードバックや外部評価を次年度の改善に活かすという、本来あるべきPDCAサイクルが機能しません。
内容・戦略の“壁”
-
「価値創造ストーリーが描けない」
国際統合報告評議会(IIRC)のフレームワークやGRIスタンダード、TCFD提言など、多様なガイドラインへの準拠を意識するあまり、情報をただ網羅するだけで当たり障りのない、メッセージ性の薄い統合報告書になってしまっているケースが散見されます。ステークホルダーが本当に知りたいのは、ガイドラインに準拠した情報ではなく、貴社が持つ独自の強み(無形資産)を活かして、いかにして社会課題を解決し、持続的な企業価値向上を実現していくのかという、説得力のある成長戦略のストーリーなのです。
-
「非財務と財務の
『つながり』を示せない」人的資本への投資や気候変動への対応といった非財務の取り組みが、将来のキャッシュフローや資本効率(ROICなど)の向上にどう結びつくのか。この財務的インパクトとの論理的な因果関係を、投資家が納得する形で示すことに多くの企業が苦慮しています。サステナビリティ戦略がビジネス戦略と連動せず、独立していると見なされれば、それは単なるコストとして評価されてしまうのです。
-
「投資家・評価機関の
視点がわからない」調査によると、統合報告書を発行した企業の41.6%が「幅広いステークホルダーのニーズを満たしているのかよく分からない」と感じています。特に、日々進化する機関投資家の関心事や、MSCI、FTSE Russellといった主要ESG評価機関の評価ロジックを正確に把握しないまま制作を進めてしまうと、多大な労力をかけたにもかかわらず評価が上がらないという結果を招きかねません。
これらの課題は、担当者個人の能力不足によるものではなく、
統合報告が単なる「報告業務」から「戦略的コミュニケーション」へとその役割を大きく変えたことに、
社内体制や制作プロセスが追いついていないという構造的な問題に起因しています。

プライム市場で評価される
「新・情報開示基準」
2022年の東証市場再編以降、プライム上場企業に対する情報開示の要求水準は、質・量ともに劇的に変化しました。
もはや「国内基準」は存在せず、グローバルな資本市場のルールが直接適用される時代です。
-
国際基準のグローバル・
ベースライン化ISSB/SSBJ基準への対応は不可避IFRS財団傘下の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表したIFRS S1(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)とIFRS S2(気候関連開示)は、投資家の情報ニーズを起点としたサステナビリティ開示の「グローバル・ベースライン」として、世界中の資本市場で参照され始めています。日本においても、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)がこれらと整合的な日本版基準の公開草案を発表しており、プライム上場企業に対しては、時価総額に応じて段階的な強制適用が見込まれています。
これらの動きは、これまで各企業の判断に基づいて開示されていたサステナビリティ情報の多くが、財務諸表と同等の信頼性、厳格性、そして企業同士を比較可能な「制度開示」へ移行することを意味します。特にIFRS S2では、TCFD提言を基礎としつつも、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量(Scope3)や、気候変動に対する具体的な移行計画の開示を要求しており、対応の難易度は格段に上がっています。 -
非財務情報の戦略的深化人的資本・自然資本開示の最前線
投資家は、企業の持続的な価値創造の源泉として、技術力やブランドといった無形資産、とりわけ「人的資本」に対して極めて強い関心を寄せています。2023年3月期より有価証券報告書での開示が義務化された「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間の賃金格差」といった指標や、内閣府の指針が示す「7分野19項目」の開示は、あくまで出発点に過ぎません。真に問われているのは、これらの指標をいかに企業独自の人材戦略と結びつけ、企業価値向上のストーリーとして語られているかなのです。
さらに、気候変動(TCFD)に続き、自然資本・生物多様性に関する情報開示の枠組みであるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の提言も公表され、企業活動が自然に与える影響と依存度についての開示も新たな潮流となっています。これらの非財務情報を単に開示項目として処理するのではなく、マテリアリティ分析を通じて自社の事業機会とリスクを特定し、経営戦略そのものに統合していく「統合思考」の実践が不可欠です。 -
「資本コストや株価を意識した経営」
についての説明責任東京証券取引所がプライム市場の約半数を占めるPBR1倍割れの企業などに対して要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」は、一過性の取り組みではありません。投資家は、企業が自社の資本コストを正確に把握した上で、それを上回る資本収益性(ROEやROIC)をいかにして達成していくのか、その具体的な計画と進捗を注視しています。
この説明責任を果たすために最も重要なコミュニケーションツールが統合報告書です。自社の現状分析、課題認識、具体的な改善策、そしてその進捗を測るKPI(重要業績評価指標)を明確に示し、投資家に対して企業価値向上の蓋然性を論理的に伝えることが、資本コストの低減と持続的な株価形成に直結するのです。

機関投資家・評価機関は
「価値創造の実証」を求めている
統合報告書は、“誰に何を”伝えるためのツールでしょうか。
最大の読者である機関投資家と、企業評価を左右する
ESG評価機関の視点を理解することが、評価向上への最短ルートです。
機関投資家(GPIF運用機関など)が
評価するポイント
世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、
国内株式の運用を委託する運用機関に対し、「優れた統合報告書」の選定を依頼しています。
その評価コメントから、投資家が真に重視するポイントが見えてきます。
-
経営トップの「生の声」と
「コミットメント」テンプレート的な挨拶ではなく、CEO自身の言葉で、事業環境への危機感、自社の強みへの確信、そして企業価値向上への強い意志が語られているかが問われます。実際に高い評価を得た伊藤忠商事のレポートは、「CEOの考えが明確に伝わってくる」「経営トップ・取締役会・現場の社員全員が企業価値向上に取り組んでいることがよくわかる」と評されています。トップメッセージは、投資家が最も期待するコンテンツの一つです。
-
独自性のある「価値創造ストーリー」と
「ビジネスモデル」他社の模倣ではない、自社ならではの歴史や強み(無形資産)を起点とした価値創造プロセスが、ロジックツリーや独自のフレームワークを用いて分かりやすく可視化されているかが重要です。「お仕着せの価値創造ストーリーもない」と評価されるように、自社の言葉でビジネスモデルと成長戦略を語り切ることが求められます。
-
戦略とKPIの明確な連動性
中期経営計画などの戦略が、具体的な財務・非財務KPIに落とし込まれ、その進捗がPDCAサイクルとして毎年トラッキング可能になっているか。投資家は、計画の実行力と目標達成への蓋然性を厳しく見ています。事業の「投資基準」や「撤退基準」を明記することも、規律ある経営姿勢を示す上で高く評価されます。
-
簡潔さと読みやすさ
情報量が多ければ良いというわけではありません。「記載内容も簡潔かつ図表とのバランスも良くてとても読みやすい」と評されるように、投資家が限られた時間の中で要点を直感的に理解できる構成、デザイン、ライティングが不可欠です。
主要ESG評価機関の
評価ロジックと対策
MSCI、FTSE Russell、Sustainalyticsといった評価機関のスコアは、
ESGインデックスへの組み入れや機関投資家の投資判断に直接影響します。
各社の評価アプローチの違いを理解し、統合報告書で戦略的に情報を開示することがスコア向上の鍵となります。
| 評価機関 | 評価アプローチ | 主な特徴 | 統合報告書で重視すべき開示戦略 |
|---|---|---|---|
| 業種内相対評価 (AAA~CCC) | 業界特有のESGリスクへのエクスポージャー(晒され度)と、それに対するマネジメント能力を同業他社と比較して評価します。ガバナンスは全社共通の基準で評価されます。 | 【戦略:ベンチマークと優位性の明示】自社が属する業界の重要ESG課題(キーイシュー)を特定し、同業他社と比較して自社のリスク管理体制やパフォーマンスがどう優れているかをデータで示します。ガバナンス体制の先進性を具体的に記述することが有効です。 | |
| エクスポージャー加重評価 (0-5点) | 企業の事業内容(ICBサブセクター)や活動地域に応じてリスク(エクスポージャー)を判定し、自社にとって重要なテーマほど高いウェイトで評価します。3つの柱(環境、社会、ガバナンス)と14のテーマで構成されています。 | 【戦略:マテリアリティと網羅性の両立】自社の事業にとって最もマテリアリティの高いテーマ(例:気候変動、人権、労働基準)について、国際基準に準拠した方針、体制、実績を詳細に開示します。特にリスクエクスポージャーが高いと判断されるテーマは重点的に記述する必要があります。 | |
| 未管理ESGリスクの絶対評価 (スコアが低いほど高評価) | 企業が直面するESGリスクのうち、企業の管理策によってもコントロールしきれない「未管理のリスク」の大きさを絶対値でスコア化します。投資家にとっての財務的リスクを直接的に示すことを目的としています。 | 【戦略:リスク管理プロセスの徹底的な可視化】特定されたマテリアルESGイシュー(MEIs)ごとに、リスクを管理するための具体的な方針、プログラム、KPI、ガバナンス体制を詳細に説明します。「何をしたか」だけでなく、「なぜそれがリスクを低減すると言えるのか」という論理を明確にすることが求められます。 |

アサヒコミュニケーションズが実現する
「評価される」統合報告書
課題を解決し、投資家から評価される統合報告書を制作するために。
私たちは単なる制作会社ではなく、貴社の企業価値向上を情報開示の側面から支援する戦略パートナーです。
私たちが提供する
4つのコア・ソリューション
-
戦略ストーリーの構築
経営トップへのヒアリングや関係部署とのワークショップを通じて、貴社の中に埋もれている価値の源泉を発掘します。ガイドラインへの準拠という守りの姿勢を超え、投資家やステークホルダーの心に響く、独自性と説得力のある「価値創造ストーリー」を共に構築します。
解決できる課題
- 「価値創造ストーリーが描けない」
- 「非財務と財務のつながりを示せない」
-
専門家による
プロジェクトマネジメント経験豊富な専門スタッフが、キックオフから納品までの全工程をファシリテートします。複雑な部門間調整、多岐にわたる情報収集、厳格なスケジュール管理を一手に引き受け、担当者様の負担を大幅に削減します。
解決できる課題
- 「人員不足」
- 「部門間調整の限界」
- 「PDCAが回らない」
-
最新動向に基づく企画提案
ISSB/SSBJ基準、人的資本・自然資本開示、PBR改善策といった最新の開示要請と投資家トレンドを完全に網羅したコンテンツを企画・提案します。毎年陳腐化することのない、一歩先を行く先進的な報告書を実現します。
解決できる課題
- 「何をどう開示すればいいかわからない」
- 「企画がマンネリ化している」
-
外部評価の向上支援
GPIFの評価ポイントや主要ESG評価機関のロジックを徹底的に分析します。スコア向上に直結する開示のポイントを具体的にアドバイスし、報告書の改善から評価機関への効果的なフィードバック支援まで、一気通貫でサポートします。
解決できる課題
- 「投資家・評価機関の視点がわからない」
- 「評価が上がらない」
外部評価だけでなく
担当者さまの負担も劇的に改善
私たちは、単なる「つくる」会社ではありません。
貴社の企業価値が、ステークホルダーに「伝わる」まで、戦略的パートナーとして徹底的に伴走します。
-
伝統的な製造メーカー A社さま
課題
主力事業が市場の構造変化によって長期的な縮小傾向にある伝統的な製造業。高付加価値な新事業への大胆な転換を進めているものの、その戦略の実現可能性について投資家など外部からの理解が追いついていない状況でした。
過去のコンプライアンス問題からの信頼回復も課題であり、新たな成長戦略を説得力をもって示す必要がありました。私たちの支援
企業が掲げる新たな中期経営計画を物語の核とし、国際的な報告フレームワークに沿って価値創造ストーリーを再構築。
新事業への「資本投下」が、具体的な「技術革新」を通じて将来の「財務的成果」にいかに結びつくかを論理的に可視化しました。成果
市場における「衰退産業の旧来型企業」という認識を、「未来志向のイノベーション企業」へと転換させるきっかけを作りました。
戦略の透明性を高めることで投資家の信頼を醸成し、長期的な企業価値向上への期待を高めることに貢献しました。 -
長年愛される食品メーカー B社さま
課題
長年の信頼と親しみやすいイメージを資産とする、消費者向けのブランド企業。一方で、その製品の原料調達における人権や環境といったグローバルなサプライチェーン上の課題への対応が問われ、ブランドイメージと事業実態との間にギャップが生じるリスクを抱えていました。
私たちの支援
国際的なサステナビリティ報告基準に基づき、サプライチェーンにおける人権・環境リスクへの取り組みを具体的に開示。持続可能な原料調達に関する数値目標や、国際的な枠組みへの参加といった検証可能な事実を明記し、説明責任を果たす姿勢を明確にしました。
成果
サプライチェーンに潜む重大なレピュテーションリスクを予防的に管理できました。倫理的な価値観を重視する現代の消費者からの共感と支持を獲得し、ブランドの魅力を次世代に向けて更新・強化することに繋がりました。
-
専門サービス企業 C社さま
課題
競争力の源泉が、専門性の高い人材や独自の組織文化といった「無形資産」にあるテクノロジー企業。しかし、その価値は財務諸表に現れにくく、なぜ高い収益性を維持できるのかという論理が外部の投資家に十分に伝わっていませんでした(情報の非対称性)。
私たちの支援
投資家を主要な読者と定め、企業として初となる統合報告書の制作を支援。独自の「企業文化」が、具体的な「人材マネジメント施策」を通じて「事業パフォーマンス」を生み出し、最終的に「財務成果」に繋がるという、人的資本を起点とした価値創造の連鎖を体系的に提示しました。
成果
企業の競争優位性の源泉を明確にし、「なぜこの会社に投資すべきか」という問いに対する説得力のある投資論理を確立しました。
経営の「見えざる資産」を可視化することで市場からの信頼を高め、より適正な企業価値評価に繋がりました。

企業価値向上への
新たな一歩を、今すぐ
高度な統合報告書を効率的に制作するには、客観的な現状把握から始まります。
まずは、貴社の課題を私たちにお聞かせください。
アサヒコミュニケーションズでは、無料オンライン相談を承ります。
専門スタッフによる
無料オンライン相談
人員不足、部門間調整の難しさ、内容のマンネリ化など、担当者さまが抱える具体的なお悩みに、経験豊富な専門家が直接お答えします(30~60分)。